
全国広報広聴研究大会
第62回 全国広報広聴研究大会
(埼玉県北本市 2025年(令和7年)開催)
公開日 : 2025年8月5日
実施報告
開会式
開会式でははじめに、主催の日本広報協会の嶋津昭会長、埼玉県の堀光敦史副知事、北本市の三宮幸雄市長から、開会の挨拶がありました。続いて、内閣府と総務省からの祝辞が寄せられました。

嶋津昭・日本広報協会会長
「自治体広報の現場でも、DXやAI、SNSなどが登場している。広報広聴に関して日頃から成果を上げられてきた皆さんは、AI等に関しても、よい道具として広報活動に十分に生かしていかれると信じている」などと挨拶。

堀光敦史・埼玉県副知事
「デジタル化が進む現在、新しい技術を取り入れた情報発信が求められている。同時に、情報過多や信頼性への懸念がある中で、正確さや公平・公正をどのように実現していくかが課題。今大会で、全国の皆さんと知識や経験を共有し、広報の新たな可能性が見いだされることを期待」しているなどと挨拶。

三宮幸雄・北本市長
「内閣総理大臣賞の受賞によって視察が増えるなど新たな交流が生まれ、関係人口も増える。今大会のような担当者同士の交流がまちの元気の源になる。市職員をはじめ、北本開催に向けて尽力されたすべての皆さんに感謝したい」などと挨拶。
表彰式
開会式に続き、「令和7年全国広報コンクール」の表彰式が行われました。全国広報コンクールは、地方自治体等の広報活動の向上を図るため、各種広報作品について審査を行い、優秀作品を表彰しています。令和7年全国広報コンクールは、5媒体10部門の参加作品448点について、今年2月から4月にかけて各部門別審査会および総合審査会を行い、特選10点、入選82点(佳作含む)を決定しました。
内閣総理大臣賞は、特選受賞団体の中から、本庄市(埼玉県)に贈られました。
各部門特選団体に総務大臣賞が、各部門入選団体に日本広報協会会長賞が、それぞれ贈られました。
また、地域の課題やニュース、人物等を積極的に取り上げ、住民の視点を生かした、特に優れている作品(各部門1作品)には読売新聞社賞が、地域の魅力やその地方ならではのニュースなど「地域の活性化や課題解決のヒント」となる2作品に、BSよしもと賞が贈られました。

写真:特選受賞団体には賞状と記念の盾が贈られました
事例発表
続いて、広報紙部門で特選を受賞した愛知県東浦町の伊藤大輔さん、広報企画部門特選(内閣総理大臣賞)を受賞した埼玉県本庄市の高柳一美さんが、それぞれの受賞作品の制作の舞台裏について発表しました。
「まだ知らない『広報ひがしうら』のセカイ」――広報紙部門特選:愛知県東浦町
特選を受賞した「広報ひがしうら」2024年12月号では、「おしえて!給食の舞台裏〜まだ知らない給食のセカイ!」と題し、学校給食の現状を紹介。
担当した伊藤さんは、「いろいろな面で方針転換を余儀なくされた」など取材・編集で苦労したエピソードや、「住民が知らない給食のリアルな面を知り、「給食をおいしく食べてほしい」という担当職員の思いを伝えることができた」といった編集後の成果を発表。
また、制作にあたっては「自分が住民だったら」という視点を心掛けていること、成功に必要な要因として「担当者の熱量」が重要であることを発表しました。

写真:東浦町の伊藤さんが広報紙制作の事例を発表
〜まちの『ファン』である関係人口をまちの『推し』へ〜まちの当事者を増やして、持続的な発展を目指す――埼玉県本庄市
本庄市のシティプロモーション事業は、「まちへの愛着を生む」きっかけとなる事業と、まち全体で受け皿となる土壌づくりの事業とが相互につながることで、効果をまち全体に広げていくことを目指しています。この事業の一つで、平成20年度から続く高校生プロジェクト「七高祭」では、企画を進める上で「企画づくりの過程から関わってもらう」ことを重視し、その結果、高校生が卒業後も地元のイベントにかかわるなど、「自走する市民」が増えていることを紹介。今後も主体的に取り組む市民などが増えること、それを応援できる組織であることなどを目指し、行動とブラッシュアップを続けていきたいと抱負を語りました。
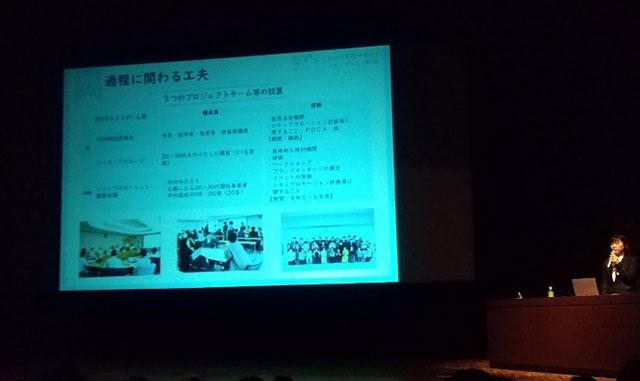
写真:本庄市の高柳さんがシティプロモーションの事例を発表
参加者も一緒に考えた あなたはどっち派?――パネルディスカッション
午後からは、パネルディスカッション「激論!自治体広報〜あなたはどっち派?〜」を開催。茨城県小美玉市の代々城衣里さん、埼玉県草加市の安高昌輝さん、埼玉県北本市の秋葉恵実さん、合同会社LOCUS BRiDGE(元埼玉県北本市)の林博司さん、埼玉県ときがわ町の保坂良輔さん、パブリシンク株式会社(元兵庫県川西市)の池田次郎さん、奈良県生駒市の村田充弘さん、奈良県王寺町の村田大地さんの8人をパネリストに、日本広報協会・藤本勝也の司会進行で行われました(アシスタント:埼玉県北本市・佐守志穂さん)。
パネルディスカッションでは、「やっぱり広報紙がまだまだ中心/これからはウェブ中心になる」「広報紙は外注/広報紙は内製」「広報は住民との関係構築を目指すべき/広報は住民の行動変容を目指すべき」「シティプロモーションは住民向け中心?/域外向け中心?」など、広報媒体制作や広報のあり方などを問うテーマについて、登壇者8人がA派、B派に分かれ、それを支持する理由や意見をぶつけ合いました。
また、会場出席者もアプリを活用し、どちらかの派に投票したり、コメントしたりする仕組みを導入。投票やコメントの結果を随時、壇上のスクリーンに投影して、登壇者がそれに対する意見を述べたり、会場出席者が直接発言したりする場面もありました。
大会のテーマにもなっている「全国に仲間づくりは必要か?」では、「人見知りなので(声をかけるのは)緊張するが、自分を高められた」「実際に会って話を聞くことで得られるものは大きい」など必要だという意見のほか、「あの自治体には負けたくないという〝敵〞も必要」や、「研修の席で隣に座った人に声をかけてみる」「まちに出てそこで仲間をつくる」など、仲間の増やし方についてのアドバイスも聞かれました。


